-
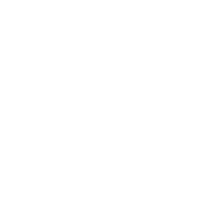
成年後見 
![]()
成年後見





成年後見制度とは、認知症や知的障害・精神障害などの理由で判断能力が十分でない方を支援し、保護するための制度です。
成年後見制度には、
◯判断能力が衰えたときに備え、判断能力が十分なうちに後見人を自分で選び契約しておく「任意後見制度」
◯判断能力の衰えた後に裁判所により後見人等を選任してもらう「法定後見制度」があります。
法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つがあります。
成年後見制度を利用するためには、法律的な手続きが必要となります。
本人の判断能力が将来衰えたときのために備え「任意後見人」となる者を自ら事前に選任し契約をしておくことを任意後見契約と言い、判断能力が衰えたときに家庭裁判所により本人が選んだ任意後見人を監督する「任意後見監督人」が選任されることで、効力が発生します。
任意後見人となる者と本人の契約は、公正証書でしなくてはなりません。
任意後見人は、本人自身が信頼できる人(例えば、家族や友人、弁護士、司法書士などの専門家)と任意後見契約を締結できます。
法定後見制度において、本人の判断能力が低い順に「後見」、「保佐」、「補助」となっており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度は、本人の保護を図るためにそれぞれ「後見人」、「保佐人」、「補助人」を家庭裁判所が選任します。
本人の代わりに契約を締結したり、本人のした不利益な契約を取り消したりする権限が与えられます。
成年後見人などは、財産の管理にとどまらず、心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない役割を任されています。 成年後見制度を利用するためには、法律的な手続きが必要となります。
◯財産管理能力の衰えた方を親族や第三者が囲い込み、他の親族が関与できないようにして財産を欲しいままに費消してしまった場合
家庭裁判所に成年後見人などの財産管理者の選任を申立てると、家庭裁判所は成年後見人として弁護士を選任し、弁護士が本人の財産を適正に管理し、本人が亡くなった際には、相続人の代表者に遺産を引き渡します。
◯本人の能力が衰え、不動産の売却や預金の解約ができない場合
成年後見人などの財産管理者を選任することで、預金の解約や不動産の売却ができ、老人ホームに入居する資金を確保し、入居契約をすることができます。
成年後見人の候補者としては、本人の家族や親族、弁護士などの専門家が挙げられますが、弁護士を成年後見人とするメリットは大きいと考えます。しかしデメリットとして成年後見人報酬が発生します。
成年後見人の職責は重大であるうえに、各法律行為に関するやり取りや家庭裁判所への定期報告など、事務的な手間も発生します。
弁護士は法律のプロであり、本人のために最善を尽くす義務があります。弁護士を成年後見人とすれば、煩雑な事務手続きを一任できるため、家族や親族は仕事や介護に専念できます。
親族同士の感情的な対立や、財産を巡る争いなどとは無縁で利害関係を持たない点が、弁護士の大きな強みです。弁護士は、親族内の状況がどうであるかにかかわらず、常に成年後見人としての職務を公正に執行することができます。
本人が遠方に住んでいる場合には、成年後見人に家族や親族を選任したとしても、適切に財産の管理のサポートはほとんどできません。弁護士を成年後見人として選任すれば、出張での対応を依頼することも可能ですし、本人の居住地域を拠点とする弁護士に依頼すれば、出張交通費を削減できます。
判断力が低下するとトラブルに巻き込まれやすくなりますが、弁護士に成年後見人を任せればトラブルに対する解決が期待できます。例えば、不要な物品を購入させられたり、不要なリフォーム工事などの契約をしてしまったとしても取消権を行使できます。弁護士なら法的理論から対抗も可能です。
高齢の親族について成年後見を申し立てる場合、相続もセットで事前に検討しておくのがよいでしょう。
弁護士には、成年後見人への就任と併せて、遺産分割・遺言書作成・遺言執行などの相談をすることもできます。
万が一、遺産分割に際してトラブルが発生した場合にも、紛争解決のサポートができる点が、弁護士特有の大きな強みです。
「後見」、「保佐」、「補助」といった法定後見の手続はお済みですか?
成年後見制度を利用ができるかどうかでやるべきことが変わってきます。
認知症と言っても色々な段階があり、軽い物忘れや日によって判断能力が変わる場合もあります。
遺産分割協議のためには自己の財産を管理する能力が必要です。一般的には、小学校低学年程度の財産管理能力があればよいと言われています。
認知症の人でも、遺産の内容や分割内容を理解して、分割案に同意する能力があれば、遺産分割協議をすることができます。
この点、参考となるのが公正証書遺言作成の際の公証人の認知に対する態度です。
公証人は、遺言者に認知があり、財産管理能力に疑いがある場合であっても、公正証書遺言を作成しその効力に関する争いは、後日遺言無効確認の訴えの中ですればよいと考えています。
認知が進行し、財産管理能力がない場合は、法定後見の申立をして、そのとおり法定代理人が遺産分割協議をすることになります。
法定後見の申立のためには医師の診断書が必要で、診断書や鑑定によって判断されるため、成年後見制度の審判が下りるまでには数か月程度かかることもあります。
成年後見の場合は、後見人が認知症の人に代わって、遺産分割協議をすることになります。
具体的には、遺産分割協議書に保佐人が同意する旨記載して、署名押印します。
保佐人の同意がない協議書は、保佐人が取り消せます(民法13条1項6号)。
遺産分割協議について代理権付与の審判がある場合は、成年後見同様、保佐人が遺産分割協議をすることになります。
補助開始の審判で、遺産分割協議が同意権付与や代理権付与の対象となります。
同意付与の場合は保佐と同様です。
代理権付与の場合は、成年後見と同様補助人が代理して遺産分割協議することになります(民法17条1項、15条3項)。
「後見」、「保佐」、「補助」といった法定後見の制度がありますが、難点は家庭裁判所への申立が必要です。
判断能力がにぶり被害にあってから周囲の人が気づくということもあり、手遅れとなることがあります。
実際、申立時に現金や株券を紛失していた事例、多額の未公開株詐欺にあっていた事例がありました。
これらを未然に防ぐ方法として、弁護士が財産管理契約と任意後見契約をして、本人の財産管理状況をチエックして、財産管理できなくなっていると判断した場合、後見監督人の選任を家庭裁判所に申立して任意後見を開始する契約が可能です。
弁護士は、弁護士会の監督下にあり、財産を横領すれば弁護士資格を失い廃業せざるおえません。
また弁護士は、裁判所への代理申立を含め法律事務全般を取り扱うことができますので、悪徳商法の被害者となった場合に、被害金の回復について訴訟や刑事告訴等の法的手続を直ちにとることも可能です。
本人が財産整理をして、判断能力がなくなった際には弁護士が任意後見人として財産を管理し、死亡後は相続人や財産を残したい人に財産を引き渡せるよう準備いたします。
初期費用 88,000円
《内訳》
財産目録の作成 33,000円
相続人の確定 55,000円
(戸籍謄本等の取得費用は別途1通1,100円+実費)
◎ 財産管理契約 110,000円
後見以前の段階で、本人の財産を弁護士が管理する契約
◎ 任意後見契約 110,000円
財産管理能力がなくなったとき、家庭裁判所に申立し、他の弁護士を後見監督人して、当弁護士が任意後見人となり財産管理し、死亡後の残余財産を相続人に引き継ぎます。
※公正証書遺言状の作成含む
※死後の遺産を、弁護士が遺言執行者となり、遺言どおりに財産が分けられるようにします。相続人たちの調停や訴訟に至るトラブルが防止できます。